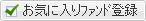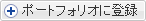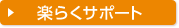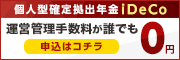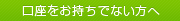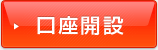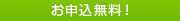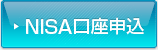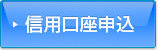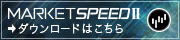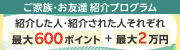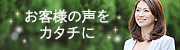【特集】TPPは日本経済に影響を与えるのか?(TPP関連銘柄特集)

日本政府が交渉への参加を決断して以来、ニュースや新聞などで連日「TPP」が話題になっています。ここではそのTPPについて詳しく取り上げてまいります。
楽天証券経済研究所アナリストの2人が「そもそもTPPとは?」「TPPと日本企業(TPP関連銘柄)」という視点で解説いたします。
そもそもTPPとは?
そもそもTPPとは?
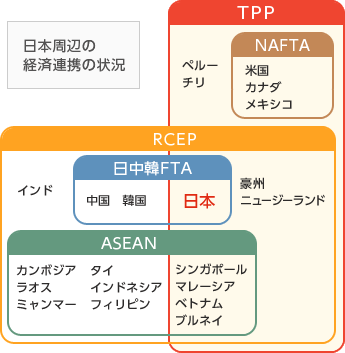
TPPとは、「 Trans - Pacific Strategic Economic Partnership Agreement 」の略で、日本語では「環太平洋戦略的経済連携協定」と言います。言葉の通り、太平洋を取り巻く国々で経済の連携を深める協定を結びましょうというもので、年内の交渉完了を目指しています。
TPPの大きな柱となっているのは、「①自由貿易の促進」と、「②国際通商ルールの統一化」です。①については、例外なき関税撤廃を原則とし、貿易商品の全品目について、関税の即時もしくは段階的に撤廃していくこととなっています。また、②については、金融システムや知的財産の保護、海外企業の参入など、国ごとに異なるビジネスのルールを統一することで、TPP参加国の企業が国境を越えて自由に活動できることを促そうとしています。
本来は、1995年に設立されたWTO(世界貿易機関)の下で、世界的な自由貿易を進める交渉が行われているのですが、実際は目立った進展がみられない状況となっているため、局地的に2国間や複数国間でFTA(自由貿易協定)やEPA(経済連携協定)を締結する動きが近年活発化しています(※)。TPPもこうした動きの一環で、より広い地域間が対象であるほか、交渉の内容もEPAに近いものとなっています。
※自由貿易協定(FTA)と経済連携協定(EPA)…外務省HPより
FTA(Free Trade Agreement、自由貿易協定)とは、ある国や地域との間で、関税をなくし、モノやサービスの自由な貿易を一層進めることを目的とした協定のことです。日本は、FTAを基礎としながら、これに加えて、投資の促進、知的財産や競争政策等の分野での制度の調和、様々な分野での協力などのより幅広い分野を対象として、経済上の連携を強化することを目的とした協定を推進しており、このような協定をEPA(Economic Partnership Agreement、経済連携協定)と呼んでいます。
現在の状況
安倍首相は3月15日にTPP参加を正式に表明しました。実際の交渉参加には、全参加国(11カ国)から承認を受ける必要がありましたが、4月20日にインドネシアで開催されたTPP閣僚会合の声明において、日本のTPP交渉参加を歓迎する旨が盛り込まれ、7月開催予定の交渉から日本が参加できる見通しとなりました。ようやくスタート地点に立つことができた格好ですが、TPPは年内の交渉完了を目指しているため、時間的な猶予が限られている中で日本がどこまでルール作りに関与できるか、ここからが本番といえます。
議論されているテーマ・分野
TPPの議論の対象は21の分野に分かれ、多岐にわたりますが、大まかに3つに分けられます。
| 分野 | 内容 | |
|---|---|---|
| 自由貿易に関するもの | ||
| 1 | 物品市場アクセス | 物品の貿易に関して、関税の撤廃や削減の方法等を定めるとともに、内国民待遇など物品の貿易を行う上での基本的なルールを定める。 |
| 2 | 原産地規則 | 関税の減免の対象となる「締約国の原産品(=締約国で生産された産品)」として認められる基準や証明制度等について定める。 |
| 3 | 貿易円滑化 | 貿易規則の透明性の向上や貿易手続きの簡素化等について定める。 |
| 4 | SPS(衛生植物検疫) | 食品の安全を確保したり、動物や植物が病気にかからないようにするための措置の実施に関するルールについて定める。 |
| 5 | TBT(貿易の技術的障害) | 安全や環境保全等の目的から製品の特質やその生産工程等について「規格」が定められることがあるところ、これが貿易の不必要な障害とならないように、ルールを定める。 |
| 6 | 貿易救済(セーフガード等) | ある産品の輸入が急増し、国内産業に被害が生じたり、そのおそれがある場合、国内産業保護のために当該産品に対して、一時的にとることのできる緊急措置(セーフガード措置)について定める。 |
| 7 | 越境サービス貿易 | 国境を越えるサービスの提供(サービス貿易)に対する無差別待遇や数量規制等の貿易制限的な措置に関するルールを定めるとともに、市場アクセスを改善する。 |
| ビジネスルールの統一化に関するもの | ||
| 8 | 政府調達 | 中央政府や地方政府等による物品・サービスの調達に関して、内国民待遇の原則や入札の手続等のルールについて定める。 |
| 9 | 知的財産 | 知的財産の十分で効果的な保護、模倣品や海賊版に対する取締り等について定める。 |
| 10 | 競争政策 | 貿易・投資の自由化で得られる利益が、カルテル等により害されるのを防ぐため、競争法・政策の強化・改善、政府間の協力等について定める。 |
| 11 | 商用関係者の移動 | 貿易・投資等のビジネスに従事する自然人の入国及び一時的な滞在の要件や手続等に関するルールを定める。 |
| 12 | 金融サービス | 金融分野の国境を越えるサービスの提供について、金融サービス分野に特有の定義やルールを定める。 |
| 13 | 電気通信サービス | 電気通信サービスの分野について、通信インフラを有する主要なサービス提供者の義務等に関するルールを定める。 |
| 14 | 電子商取引 | 電子商取引のための環境・ルールを整備する上で必要となる原則等について定める。 |
| 15 | 投資 | 内外投資家の無差別原則(内国民待遇、最恵国待遇)、投資に関する紛争解決手続等について定める。 |
| 16 | 環境 | 貿易や投資の促進のために環境基準を緩和しないこと等を定める。 |
| 17 | 労働 | 貿易や投資の促進のために労働基準を緩和すべきでないこと等について定める。 |
| TPPの運用に関するもの | ||
| 18 | 制度的事項 | 協定の運用等について当事国間で協議等を行う「合同委員会」の設置やその権限等について定める。 |
| 19 | 紛争解決 | 協定の解釈の不一致等による締約国間の紛争を解決する際の手続きについて定める。 |
| 20 | 協力 | 協定の合意事項を履行するための国内体制が不十分な国に、技術支援や人材育成を行うこと等について定める。 |
| 21 | 分野横断的事項 | 複数の分野にまたがる規制や規則が、通商上の障害にならないよう、規定を設ける。 |
※内閣府の資料より楽天証券作成
TPP参加の意義
実は、日本はTPP交渉参加国のうち、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの4カ国を除く、すべての国(7カ国)とすでにEPAを締結しています。また、TPPに関する自民党の公約は、「例外なき関税撤廃を前提とする限り、TPP交渉には参加しない」というものでした。大幅に遅れて参加してきた日本の言い分が交渉の場でどこまで通るのかも未知数ですし、国内には依然として反対意見があり、そもそもTPPに参加するメリットはあるのかという見方があります。
日本がTPPに参加する意義として考えられるのは、まずはTPPの規模です。TPPの交渉参加国は日本を含めて12カ国ですが、その経済規模は世界のGDPの約40%、世界貿易の約3分の1を占め、EUをも上回ります。巨大経済圏に組み込まれることによる、経済的・政治外交的なメリットが素直に挙げられます。
ただし、TPP参加の本当の意義は別のところにあります。日本は現在TPP以外にも多くの通商交渉を抱えています。中国・韓国との3国間FTA交渉をはじめ、EUとのEPA交渉も始まっています。さらに、ASEAN10カ国と周辺主要6カ国とのあいだでも、RCEP(東アジア地域包括的経済連携協定)というEPA交渉も開始されます。TPPに限らず、世界的に多国間・地域間の通商ルールを決めていくという大きな世の中の流れが背景にあります。
確かに、これまで国内の規制などで保護されてきた分野からしてみれば、厳しい競争環境にさらされることになりますが、その一方で、多くの国や地域との間でビジネスチャンスが拡大することにもつながります。アベノミクスの3本目の矢は「成長戦略」ですが、日本は今後、人口の減少や超高齢化社会を迎えるため、国内の経済規模や需要の大きな拡大は見込みにくく、海外の成長を有効に取り込んで行くことが重要になってきます。
TPPと日本企業(TPP関連銘柄)
 日本はTPP交渉への参加を決断
日本はTPP交渉への参加を決断
TPP(環太平洋経済連携協定)は、アメリカ、カナダ、メキシコ、ペルー、チリ、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、マレーシア、ベトナム、ブルネイの計11カ国が、全貿易品目の関税ゼロと各種非関税障壁の撤廃を目指して交渉しているものです。97~98%の自由化率を目指していると言われています。今年中の交渉妥結を目指しています。
2013年4月20日、アメリカ、オーストラリアなどTPP交渉参加11カ国は、閣僚会合を開き、日本のTPP交渉への参加を歓迎する声明を発表しました。これで日本は、7月からの交渉に正式に参加する見通しとなりました。民主党の野田前政権が参加を表明して以来大きな議論の的となってきましたが、自民党の安倍政権になってようやく交渉参加の運びとなりました。今後は年内の交渉妥結に向けてスピード交渉となる見通しです。日本が加わることで、TPPは世界のGDPの約40%、世界の貿易額の3分の1をカバーすることになります。
本稿では、TPPが日本の各産業にどのような影響を与えるかを簡単に考察します。
表1 TPP交渉参加国
| 名目GDP 100万ドル |
人口 | 一人当たりGDP ドル |
輸出額 100万ドル |
対日輸出額 100万ドル |
輸入額 100万ドル |
対日輸入額 100万ドル |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 15,075,700 | 31169万人(2011年) | 48,328 | 1,480,432 | 65,706 | 2,207,824 | 128,925 |
| カナダ | 1,738,953 | 3435万人(2011年) | 50,496 | 461,348 | 11,450 | 460,426 | 9,467 |
| メキシコ | 1,154,470 | 1億1,234万人(2010年) | 10,146 | 349,375 | 2,252 | 350,843 | 16,494 |
| ペルー | 176,761 | 2,822万人(2010年) | 5,904 | 46,268 | 2,175 | 36,967 | 1,307 |
| チリ | 248,585 | 1,725万人(2011年) | 14,403 | 81,411 | 9,009 | 70,619 | 2,958 |
| オーストラリア | 1,515,003 | 2,270万人(2011年) | 66,371 | 274,205 | 52,747 | 259,380 | 20,933 |
| ニュージーランド | 163,226 | 440万人(2011年) | 35,973 | 38,268 | 2,746 | 38,102 | 2,362 |
| シンガポール | 259,824 | 518万人(2011年) | 49,271 | 409,246 | 18,382 | 365,450 | 26,208 |
| マレーシア | 278,671 | 2,855万人(2011年) | 10,085 | 226,977 | 26,133 | 187,658 | 21,347 |
| ベトナム | 123,600 | 8,784万人(2011年) | 1,374 | 96,906 | 10,781 | 106,750 | 10,400 |
| ブルネイ | 15,600 | 39.9万人(2012年) | 36,521 | 156.5億 ブルネイドル |
4779億円 | 37.0億 ブルネイドル |
150億円 |
| 日本 | 5,866,540 | 1億2751万人(2012年) | 45,870 | 820,800 | 853,100 |
注:ジェトロ資料より楽天証券作成、数字は原則として2011年。ブルネイは外務省。1ブルネイドル=約80円。
 自動車
自動車
自動車業界は日本の産業界の中でTPP交渉参加の最大の恩恵を受けると言えます。表1はTPP交渉参加国の経済の詳細、表2は各国の自動車の輸入関税ですが、交渉参加国の中で最大の経済を持つアメリカは乗用車に2.5%、商用車に25%の輸入関税を設けています。これがなくなれば、アメリカの自動車市場で大きな存在感を持つ日本にとって有利になると思われます。
また、他の交渉参加国でも、人口約8700万人のベトナムが2013年で78%の高率関税を設けています。マレーシアも15%の関税を設けています。これらの関税がなくなれば、日本からの輸出や、日本メーカーが持っている海外工場からの輸出が活発になることが予想されます。
ただし、話はそう単純ではなく、日本が交渉参加するに当たっての事前協議の結果、アメリカは自動車関税の解消をできるだけ先延ばしすることになりました。最大10年間の先延ばしになりますが、実際のところ関税を引き下げるかどうか不透明です。カナダともアメリカ同様事前協議することになります。オーストラリアとは別途締結した日豪EPA(経済連携協定)で乗用車5%の関税を残すことになりました。従って、他の国に関しても、直ちに自動車関税がゼロになると考えるには無理がありそうです。
ただし、今の関税が維持されても、日本の自動車メーカーが困ることは実はなさそうです。自動車の世界では「消費地生産主義」が現在の大きな流れになっています。即ち販売する国やその近隣で税制、立地等で生産が有利な国での現地生産が一般的になっています。そのため日本からの輸出は技術漏洩を防ぐ必要があるエコカーや、生産量が少ない高級車に限られるようになっているのです。そのため、仮に自動車の輸入関税がゼロになっても、直ちに自動車貿易が活発になるわけではなさそうです。ただし、日本のメーカーにとっては、現地生産か輸出かという事業の選択肢が増えることになります。
また、TPPによって貿易が活発になり、それが各国の経済成長に寄与することになれば、自動車販売が増え、結果的に日本の自動車メーカーにとってメリットが発生するだろうということは言えるでしょう。
なお、アメリカから日本の軽自動車規格に対して、これを非関税障壁として撤廃するよう要求が出されています。軽自動車は税金で優遇されているというのですが、実は軽自動車の購入者が支払う税金は、販売価格に含まれているものと消費税とを合わせて、アメリカの自動車関連税とほぼ同じであり、日本の登録車の税金のほうがアメリカのそれよりも高いのです。アメリカ車が日本で売れないのは、アメリカ自動車メーカーの努力不足も一因と思われます。
また、軽自動車は日本では特に地方で人々の足となっており、新興国で人気がある1000CC前後の大衆車を開発、生産する際の技術基盤でもあります。日本が手放すことはないと言ってよいでしょう。ここから見ても、TPPの交渉にはかなりの困難が予想されます。
表2 各国の自動車輸入関税
| 乗用車 | 商用車 | |
|---|---|---|
| アメリカ | 2.5% | 25.0% |
| カナダ | 6.1% | |
| オーストラリア | 5.0% | |
| マレーシア | 15.0% | |
| ベトナム | 78.0% | |
| 日本 | 0.0% | 0.0% |
出所:楽天証券作成
 農業、農産物、加工食品
農業、農産物、加工食品
日本は多くの農産物、乳製品、食品の原材料、半製品などに高率の輸入関税をかけています(表3)。日本の農業は兼業農家が多いため、集約化が進んでおらず、その結果、国際競争力がありません。そのため、輸入品から農業を守り食料自給率を維持することが、農産物に高率の輸入関税をかける大義名分になっています。
ただし、日本の農業の国際競争力に対しては様々な意見があり、例えば日本のコメや牛肉はアジア各国の富裕層に人気があります。果物もそうです。日本の農業に輸出競争力があるかどうかは、より大規模にやってみなければわからないと思われます。
実際、牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵など比較的関税が低い分野では、輸出市場の開拓に成功した例や、輸入品と互角に競争している例を見出すことができます。これらの品目は段階的に輸入関税を引き下げており、政府の集約化、強化政策もあって、大規模化が進んだケースが多く見られます。コメや乳製品でも時間をかければ、今より低い関税でも日本の農業を維持していけるという考え方はできると思われます。
ただし、関税をゼロにするには無理があるかもしれません。また、段階的に関税を引き下げる場合でも最終的に到達する関税の数字によっては、TPP交渉国との間で、あるいは日本国内で揉める可能性が高いと思われます。特に米と乳製品は、農機、農協(金融)、流通、乳製品の加工工場などサプライチェーンが長く、関与している人たちも多いため、雇用の問題、農協の金融問題(貸し金の焦げ付きなど)に発展する可能性があります。特に米価が急低下した場合は、農協の金融問題になりかねず、乳製品が海外品との競争に負けた場合は、全国にある乳製品工場の存続と雇用の問題になると思われます。
ちなみに、麦や脱脂粉乳などの関税が下がればパンや乳製品のコストが安くなってパンメーカー、乳製品メーカーにとってプラスになるという考え方はあると思われます。しかし一方で、TPPが呼び水となって、日本に対する製品輸出を強化する企業が出てきた場合どうするのかという問題があります。例えば、ニュージーランドの国営企業フォンテラは年間売上高約1兆6000億円の世界有数の乳製品会社であり、もし日本の乳製品の輸入関税がゼロになるか、十分下がってフォンテラが対日輸出を本格化させると、日本の乳製品メーカーは大きな打撃を受ける可能性があります。
これはコメでも起こりうることであり、もし日本の大手商社、食品卸、大手流通グループなどが、アジア各国で日本の銘柄米の作付けに成功し、それを日本で販売したならば、それなりの成功を収めるかもしれませんが、日本の農家は打撃を受ける可能性があります。
なお、日本政府の試算では、関税ゼロを実施して、各種の補助策を行わない場合、自動車輸出や消費、投資の増加分が農業生産の減少分を上回り、実質GDPが3.2兆円増加するとあります。ただし、これは何も対策をとらない場合であり、実際にはこれに政府の補助金や各種支援策のプラスマイナスを加える必要があるでしょう。
表3 日米の輸入関税(主なもの)
| 日本の農産物の輸入関税 | |
|---|---|
| コメ | 778% |
| 小麦 | 252% |
| 脱脂粉乳 | 218% |
| チーズ | 22.4~40% |
| 牛肉 | 38.5% |
| アメリカの輸入関税 | |
|---|---|
| トラック(商用車) | 25% |
| ベアリング | 9% |
| ポリエステル | 6.5% |
| カラーテレビ | 5% |
| 工作機械 | 3.3~4.4% |
| 乗用車 | 2.5% |
出所:各種資料より楽天証券作成
表4 TPPによる農産物の生産減少度合いの試算(主なもの)
| 生産減少率 | 生産減少額(億円) | |
|---|---|---|
| コメ | 32% | 10,100 |
| 小麦 | 99% | 770 |
| 大麦 | 79% | 230 |
| 砂糖 | 100% | 1,500 |
| でんぷん原料作物 | 100% | 220 |
| 牛乳・乳製品 | 45% | 2,900 |
| 牛肉 | 68% | 3,600 |
| 豚肉 | 70% | 4,600 |
| 小豆 | 71% | 150 |
| 落花生 | 40% | 120 |
| 加工用トマト | 100% | 270 |
| 鶏肉 | 20% | 990 |
| 鶏卵 | 17% | 1,100 |
| 農産物合計 | 26,600 | |
| 林水産物合計 | 3,000 | |
| 農林水産物総合計 | 約3兆円 |
注:数字は概数
出所:農水省より楽天証券作成
図1
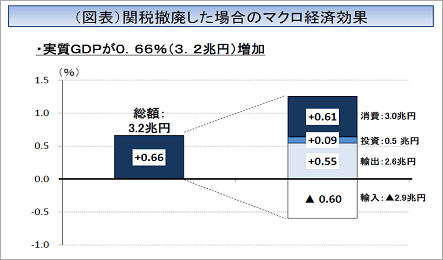
出所:政府試算2013年3月
 国内外で議論が錯綜する可能性も
国内外で議論が錯綜する可能性も
日本の自動車業界の場合は、もともと国際競争力のあるセクターなので、関税ゼロは基本的に歓迎であると思われます。しかし、農業、乳製品など現時点で高率関税で守られている業界は、いきなり関税ゼロにすると業界の存続が困難になると思われます。そこで、国内外で妥協が必要になります。要するに自民党が言う「聖域5品目」(コメ、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物(サトウキビなど))です。しかし、妥協が過ぎるとTPPの意味が希薄になりかねません。交渉期限(今年中)が延長される可能性もあると思われます。
そもそも、何故日本がTPPに参加しなければならないのかという問題もあります。TPPは太平洋諸国を貫く経済協定となり、いずれ中国も無視できなくなるだろうから、日本は今のうちにルール作りに参加すべきであるという意見、TPPは中国に対する安全保障の側面を持つという意見などがあります。ただし、TPPの中味を見ると、日本が得ることの出来る利益は少なく、損失は大きい感じがします。
それを国際政治や安全保障面でのプラス面(要するに太平洋を取り巻く各国の仲間に入っておかなければ安心できないということです)が補うことができるかどうか、今後の交渉の推移を見守る必要がありそうです。
 TPP関連銘柄
TPP関連銘柄
TPPの中身が日本にとってどうなるか不透明な状況ですから、ここで挙げる銘柄はあくまでも参考です。
自動車セクターの各社、乗用車メーカーで、トヨタ自動車、本田技研工業、日産自動車、富士重工業、マツダ、商用車メーカーで、日野自動車、いすゞ自動車、間接的にデンソー、アイシン精機などの自動車部品メーカーは、中長期的にTPPのメリットを受けると思われます。ただし、TPPに参加しなくとも、すでに現地生産の動きが加速していますので、デメリットは少ないと思われます。また、日本の自動車メーカーにとって重要国であるタイとインドネシアはTPPに入っておらず、これらの国は日本とは個別に経済連携協定を結んでいます。
大手商社(三菱商事、伊藤忠商事、丸紅など)、食品卸(三菱食品、伊藤忠食品など)、コメ卸(木徳神糧など)、大手流通グループ(イオン、セブン&アイ・ホールディングスなど)は、海外米、海外食品の輸入(開発も含む)、海外での日本の銘柄米の作付け、日本のコメなどの作物や食品の海外への輸出を行う可能性があります。ただし、海外の大手メーカーが直接日本に上陸する可能性もありますので、ポジティブな話ばかりではないかもしれません。
農機メーカー(クボタ、井関農機)も、競争力が強化された日本の農家が農機を増やすことはあると思われますが、兼業農家が撤退するマイナス面もあると思われます。また、海外で日本向け輸出を目指してコメなどを作付けする動きが広がれば、業績にはプラスになると思われます。
表5 TPP関連銘柄
| テーマ | 企業名 |
|---|---|
| 乗用車輸出 | トヨタ自動車、本田技研工業、日産自動車、富士重工業、マツダ |
| 商用車 | 日野自動車、いすゞ自動車 |
| 農業機械 | クボタ、井関農機 |
| 総合商社 | 三菱商事、三井物産、住友商事、伊藤忠商事、丸紅 |
| 食品卸 | 三菱食品、伊藤忠食品 |
| コメ卸 | 木徳神糧 |
| 大手流通 | イオン、セブン&アイ・ホールディングス |
出所:楽天証券作成
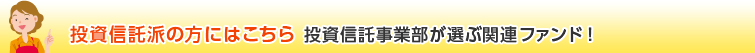
TPPで成長する日本に期待!
日本がTPPに参加することで恩恵を享受できると期待されている業界は、政府による対策が期待される農業だけではありません。関税の撤廃が商社や自動車業界に貢献すると期待されています。
トヨタ自動車およびそのグループ会社のうち、日本の取引所第一部に上場している株式に投資を行う銘柄です。組入銘柄上位には、トヨタ自動車、デンソーをはじめダイハツや日野自動車もあります。
自動車やトラックの関税が撤廃されるとトヨタ自動車関連の業績向上の恩恵に期待できるかもしれません。
ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド(日本株)【愛称】スマイル・ジャパン【三菱UFJ投信】
日本の競争力のある優良企業の株式の中から、株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行う銘柄。組入銘柄上位には、トヨタ自動車や日産自動車が、商社では伊藤忠商事や丸紅などが含まれます。
ネット証券専用の銘柄であることも注目ポイント。比較的、低コストなので1,000円からの積立でコツコツと投資してみるのもいいのではないでしょうか。
TPPで成長する世界に期待!
TPP参加国は、日本以外にも米国、カナダ、オーストラリア、ベトナム、マレーシア、シンガポールなど、13カ国にのぼります。(日本は参加意欲表明国)それらの中には、アセアン加盟国の半数である5カ国が含まれ、これらの国にもさらなる成長期待が寄せられます。
アセアン加盟国の取引所上場株式のうち、各国、地域、各業種等において競争力があり、かつ財務健全性を備えた優良銘柄を中心に厳選し投資するファンドで、原則として為替ヘッジを行わず運用します。組入上位国には、TPP参加国である、シンガポール、マレーシアが含まれます。
買付手数料が0円(ノーロード)であることも嬉しいポイントです。
JFアセアン成長株オープン【JPモルガン・アセット・マネジメント】
東南アジア諸国連合(ASEAN)加盟国のいずれかで上場または取引されている株式および「ASEAN」関連株式等の中から、収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資する銘柄で、原則として為替ヘッジを行わず運用します。組入銘柄の上位には、シンガポールやタイの銀行が含まれます。
まだ口座をお持ちでない方
国内株式のリスクと費用について
■国内株式 国内ETF/ETN 上場新株予約権証券(ライツ)
【株式等のお取引にかかるリスク】
株式等は株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等、ライツは転換後の価格や評価額の変動等により、損失が生じるおそれがあります。※ライツは上場および行使期間に定めがあり、当該期間内に行使しない場合には、投資金額を全額失うことがあります。
レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意点
上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN(※)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
- レバレッジ型、インバース型のETF及びETNの価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
- 上記の理由から、レバレッジ型、インバース型のETF及びETNは、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
- レバレッジ型、インバース型のETF及びETNは、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただく、またはコールセンターにてお尋ねください。
※「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
【信用取引にかかるリスク】
信用取引は取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
【株式等のお取引にかかる費用】
国内株式の委託手数料は「ゼロコース」「超割コース」「いちにち定額コース」の3コースから選択することができます。
〔ゼロコース(現物取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。
但し、原則として当社が指定するSOR(スマート・オーダー・ルーティング(※1))注文 のご利用が必須となります。(当社が指定する取引ツールや注文形態で発注する場合を除きます。)
ゼロコースをご利用される場合には、当社のSORやRクロス(※2)の内容を十分ご理解のうえでその利用に同意いただく必要があります。
※1 SORとは、複数市場から指定条件に従って最良の市場を選択し、注文を執行する形態の注文です。
※2 「Rクロス」は、楽天証券が提供する社内取引システム(ダークプール(※3))です。
※3 ダークプールとは、証券会社が投資家同士の売買注文を付け合わせ、対当する注文があれば金融商品取引所の立会外市場(ToSTNeT)に発注を行い約定させるシステムをいいます。
〔ゼロコース(信用取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。
但し、原則として当社が指定するSORのご利用が必須となります。(当社が指定する取引ツールや注文形態で発注する場合を除きます。)
〔超割コース(現物取引)〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引金額 取引手数料
5万円まで 55円(税込)
10万円まで 99円(税込)
20万円まで 115円(税込)
50万円まで 275円(税込)
100万円まで535円(税込)
150万円まで640円(税込)
3,000万円まで1,013円(税込)
3,000万円超 1,070円(税込)
〔超割コース(信用取引)〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引金額 取引手数料
10万円まで 99円(税込)
20万円まで 148円(税込)
50万円まで 198円(税込)
50万円超 385円(税込)
超割コース大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブページをご参照ください。
〔超割コース 大口優遇(現物取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。
〔超割コース 大口優遇(信用取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。
〔いちにち定額コース〕
1日の取引金額合計(現物取引と信用取引合計)で手数料が決まります。
1日の取引金額合計 取引手数料
100万円まで0円
200万円まで 2,200円(税込)
300万円まで 3,300円(税込)
以降、100万円増えるごとに1,100円(税込)追加。
※1日の取引金額合計は、前営業日の夜間取引と当日の日中取引を合算して計算いたします。
※一般信用取引における返済期日が当日の「いちにち信用取引」、および当社が別途指定する銘柄の手数料は0円です。これらのお取引は、いちにち定額コースの取引金額合計に含まれません。
【かぶミニ®(単元未満株の店頭取引)にかかるリスクおよび費用】
- リスクについて
- かぶミニ®の取扱い銘柄については市場環境等により、取扱いを停止する場合があります。
- 費用について
- 売買手数料は無料です。
かぶミニ®(単元未満株の店頭取引)は、当社が自己で直接の相手方となり市場外で売買を成立させます。そのため、取引価格は買付時には基準価格に一定のスプレッド(差額)を上乗せした価格、売却時には基準価格に一定のスプレッド(差額)を差し引いた価格となります(1円未満の端数がある場合、買付時は整数値に切り上げ、売却時は切り捨て)。なお、適用されるスプレッドは当社ウェブサイトにて開示していますが、相場環境の急変等により変動する場合があります。
- カスタマーサービスセンターのオペレーターの取次ぎによる電話注文は、上記いずれのコースかに関わらず、1回のお取引ごとにオペレーター取次ぎによる手数料(最大で4,950円(税込))を頂戴いたします。詳しくは取引説明書等をご確認ください。
- 信用取引には、上記の売買手数料の他にも各種費用がかかります。詳しくは取引説明書等をご確認ください。
- 信用取引をおこなうには、委託保証金の差し入れが必要です。最低委託保証金は30万円、委託保証金率は30%、委託保証金最低維持率(追証ライン)が20%です。委託保証金の保証金率が20%未満となった場合、不足額を所定の時限までに当社に差し入れていただき、委託保証金へ振替えていただくか、建玉を決済していただく必要があります。
レバレッジ型ETF等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、30%を上回る委託保証金が必要な場合がありますので、ご注意ください。
【貸株サービス・信用貸株にかかるリスクおよび費用】
(貸株サービスのみ)
- リスクについて
- 貸株サービスの利用に当社とお客様が締結する契約は「消費貸借契約」となります。株券等を貸付いただくにあたり、楽天証券よりお客様へ担保の提供はなされません(無担保取引)。
(信用貸株のみ) - 株券等の貸出設定について
- 信用貸株において、お客様が代用有価証券として当社に差入れている株券等(但し、当社が信用貸株の対象としていない銘柄は除く)のうち、一部の銘柄に限定して貸出すことができますが、各銘柄につき一部の数量のみに限定することはできませんので、ご注意ください。
(貸株サービス・信用貸株共通)
- 当社の信用リスク
- 当社がお客様に引渡すべき株券等の引渡しが、履行期日又は両者が合意した日に行われない場合があります。この場合、「株券等貸借取引に関する基本契約書」・「信用取引規定兼株券貸借取引取扱規定第2章」に基づき遅延損害金をお客様にお支払いいたしますが、履行期日又は両者が合意した日に返還を受けていた場合に株主として得られる権利(株主優待、議決権等)は、お客様は取得できません。
- 投資者保護基金の対象とはなりません
- 貸付いただいた株券等は、証券会社が自社の資産とお客様の資産を区別して管理する分別保管および投資者保護基金による保護の対象とはなりません。
- 手数料等諸費用について
- お客様は、株券等を貸付いただくにあたり、取引手数料等の費用をお支払いいただく必要はありません。
- 配当金等、株主の権利・義務について
- 貸借期間中、株券等は楽天証券名義又は第三者名義等になっており、この期間中において、お客様は株主としての権利義務をすべて喪失します。そのため一定期間株式を所有することで得られる株主提案権等について、貸借期間中はその株式を所有していないこととなりますので、ご注意ください。(但し、信用貸株では貸借期間中の全部又は一部においてお客様名義のままの場合もあり、この場合、お客様は株主としての権利義務の一部又は全部が保持されます。)株式分割等コーポレートアクションが発生した場合、自動的にお客様の口座に対象銘柄を返却することで、株主の権利を獲得します。権利獲得後の貸出設定は、お客様のお取引状況によってお手続きが異なりますのでご注意ください。貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金については、発行会社より配当の支払いがあった後所定の期日に、所得税相当額を差し引いた配当金相当額が楽天証券からお客様へ支払われます。
- 株主優待、配当金の情報について
- 株主優待の情報は、東洋経済新報社から提供されるデータを基にしており、原則として毎月1回の更新となります。更新日から次回更新日までの内容変更、売買単位の変更、分割による株数の変動には対応しておりません。また、貸株サービス・信用貸株内における配当金の情報は、TMI(Tokyo Market Information;東京証券取引所)より提供されるデータを基にしており、原則として毎営業日の更新となります。株主優待・配当金は各企業の判断で廃止・変更になる場合がありますので、必ず当該企業のホームページ等で内容をご確認ください。
- 大量保有報告(短期大量譲渡に伴う変更報告書)の提出について
- 楽天証券、または楽天証券と共同保有者(金融商品取引法第27条の23第5項)の関係にある楽天証券グループ会社等が、貸株対象銘柄について変更報告書(同法第27条の25第2項)を提出する場合において、当社がお客様からお借りした同銘柄の株券等を同変更報告書提出義務発生日の直近60日間に、お客様に返還させていただいているときは、お客様の氏名、取引株数、契約の種類(株券消費貸借契約である旨)等、同銘柄についての楽天証券の譲渡の相手方、および対価に関する事項を同変更報告書に記載させていただく場合がございますので、予めご了承ください。
- 税制について
- 株券貸借取引で支払われる貸借料及び貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金相当額は、お客様が個人の場合、一般に雑所得又は事業所得として、総合課税の対象となります。なお、配当金相当額は、配当所得そのものではないため、配当控除は受けられません。また、お客様が法人の場合、一般に法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。税制は、お客様によりお取り扱いが異なる場合がありますので、詳しくは、税務署又は税理士等の専門家にご確認ください。
投資信託のリスクと費用について
投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。
投資信託の取引にかかるリスク
- 主な投資対象が国内株式
- 組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 主な投資対象が円建て公社債
- 金利の変動等による組み入れ債券の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 主な投資対象が株式・一般債にわたっており、かつ、円建て・外貨建ての両方にわたっているもの
- 組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託の取引にかかる費用
各商品は、銘柄ごとに設定された買付又は換金手数料(最大税込4.40%)およびファンドの管理費用(含む信託報酬)等の諸経費をご負担いただく場合があります。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
- お買付時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
- 「買付手数料」:ファンドによって異なります。
- 保有期間中に間接的にご負担いただく主な費用
- 「ファンドの管理費用(含む信託報酬)」:ファンドによって異なります。
- ご換金時にお客様に直接ご負担いただく主な費用
- 「信託財産留保額」「換金手数料」:ファンドによって異なります。
買付・換金手数料、ファンドの管理費用(含む信託報酬)、信託財産留保額以外にお客様にご負担いただく「その他の費用・手数料等」には、信託財産にかかる監査報酬、信託財産にかかる租税、信託事務の処理に関する諸費用、組入有価証券の売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息等がありますが、詳細につきましては「目論見書」で必ずご確認いただきますようお願いいたします。
また、「その他の費用・手数料等」については、資産規模や運用状況によって変動したり、保有期間によって異なったりしますので、事前に料率や上限額を表示することはできません。
毎月分配型・通貨選択型ファンドに関するご注意について
投資信託は、預貯金とは異なり元本が保証されている金融商品ではありません。下記コンテンツでは、毎月分配型ファンドの分配金の支払われ方および通貨選択型の収益に関するご案内をしております。投資家の皆様につきましては、当該ファンドへの投資をご検討なさる前にぜひご確認くださいますようお願い申し上げます。
投資信託に関する情報提供について
- 楽天証券株式会社がウェブページ上で掲載している投資信託関連ページは、お取引の参考となる情報の提供を目的として作成したものであり、投資勧誘や特定銘柄への投資を推奨するものではありません。
- 各投資信託関連ページに掲載している投資信託は、お客様の投資目的、リスク許容度に必ずしも合致するものではありません。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
- 各投資信託関連ページで提供している個別投資信託の運用実績その他の情報は、当該投資信託の今後の運用成果を予想または示唆するものではなく、また、将来の運用成果をお約束するものでもありません。
(楽天証券分類およびファンドスコアについて)
- 楽天証券ファンドスコアは、「運用実績」を一定の算出基準に基づき定量的に計算したもので今後の運用成果を予想または示唆するものではなく、将来の運用成果をお約束するものでもありません。最終的な投資判断は、運用コスト、残高の規模、資金流出入額、運用プロセス、運用体制等を考慮し、お客様ご自身でなさるようお願いいたします。
- 情報提供:株式会社QUICK
各投資信託関連ページに掲載している情報(以下「本情報」という)に関する知的財産権は、楽天証券株式会社、株式会社QUICKまたは同社の情報提供元(以下三社を合わせて「情報提供元」という)に帰属します。本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じた損害について、情報提供元は原因の如何を問わず一切の責任を負いません。本情報の内容については、蓄積・編集加工・二次加工を禁じます。また、予告なしに変更を行うことがあります。
お客様へのご注意
よくあるご質問
ポートフォリオ機能・お気に入り銘柄機能
楽天証券へ資料請求して、今すぐご利用いただけます。
「ログイン前の登録銘柄と同期する」設定をしていただくことでご利用いただけます。