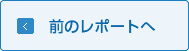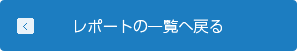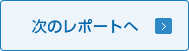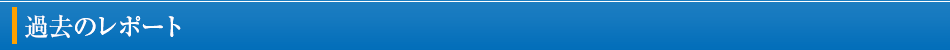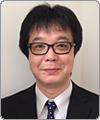- 現在地
- ホーム > マーケット情報 > レポート・コラム&コメント > 株式 > 足立武志「知って納得!株式投資で負けないための実践的基礎知識」 > 第336回 日銀が買い入れる新たなETFの正体と個人投資家の戦略
5月6日、日銀は年間3,000億円の別枠で買い入れるETFのもととなる3つの株価指数を選定しました。今後、該当するETFに日銀の購入資金が流入することになります。これらの内容と、個人投資家として特別な戦略を取る必要があるのかどうかを考えていきます。
「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するためのETF」とは?
日本銀行は、ホームページにて、ETFやREITを毎営業日ごとにどれだけ買い入れたかを公表しています。このフォーマットが、今年の4月以降変わりました。何が変わったかというと、ETFの買い入れ額の欄が2列になり、そのうちの1つに「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するためのETF」という欄が設けられたのです。これはいったいどのようなものなのでしょうか。
話は昨年の12月にさかのぼります。昨年(平成27年)の12月18日の日銀金融政策決定会合にて、日銀のETF買い入れ枠を従来の3兆円から3,000億円増加させることを決定しました。そしてその3,000億円の枠による買い入れ対象として、「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業」の株式をETFへの投資という形で購入することとしたのです。
その結果、今年の4月以降、毎営業日12億円ずつ、「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するためのETF」を購入しているのが現時点での状況です。
新しい株価指数に連動するETFがいよいよ今月上場
現在は「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するためのETF」そのものがないため、4月以降の毎営業日ごとの12億円は、JPX日経400に連動したETFの購入に充てているようです。そんな中日銀は5月6日、「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するためのETF」のもとになる株価指数として、以下の3つを選定したと発表しました。
- MSCI日本株人材設備投資指数
- 野村企業価値分配指数
- JPX/S&P設備・人材投資指数
さらに、上記3つの株価指数に連動するETFも近日上場予定となっています。①と②は5月19日、③は5月25日上場です。
- ダイワ上場投信-MSCI日本株人材設備投資指数(1479)
- NEXTFUNDS野村企業価値分配指数連動型上場投信(1480)
- 上場インデックスファンド日本経済貢献株(1481)
新しい株価指数は「アベノミクス政策」に応えている企業を対象?
ところで、企業の永続的な発展のためには、将来に向けての種まきが必要です。それが設備や人材に対しての積極的な投資です。そのため、設備・人材投資に積極的な企業を選択して、それらに重点的に投資することで、TOPIXといった日本株全体の値動きを示す株価指数よりも高い運用成果が期待できるという理屈は間違ってはいないでしょう。
その一方、なぜ今になってこうした株価指数を設定するかと言えば、やはりアベノミクスの政策を後押しするという意味合いが強いのではないかと個人的には思います。景気浮揚を目指したい安倍政権としては、企業に対して積極的に設備投資をしてもらいたいし、積極的に人材を登用して厚遇してもらいたいと思っているはずです。
企業側にとっては、日銀がETFを通じて設備・人材投資に積極的な企業の株式を購入したとしても直接的なメリットはありません。ただ、企業経営者としては株価は低いより高い方が良いのは確かですから、ETFを通じた資金流入という形によって株価の下支えという効果は期待できそうです。
個人投資家はどのように対応すればよいか
では、私たち個人投資家は、この新しい株価指数に連動するETFを積極的に投資対象として考慮する必要はあるのでしょうか。筆者個人的には、この新しいETFを積極的に買うまでのことはないと現時点では感じています。
新しく設定される3つの指数のうち、「野村企業価値分配指数」の構成銘柄および構成比率をみると、時価総額の高いいわゆる大企業にウェイトが高く設定されています。そのため、おそらく値動きはTOPIXなど、日本株全体を表す株価指数とそれほど大きく異ならないのではないかと思っています。また、年間3,000億円程度の金額では、大企業の株価を上げることは難しいと思われます。
大企業も、将来の生き残りをかけて積極的に設備・人材投資をすることは非常に素晴らしいことだと筆者も思います。しかし、それと株価とは別問題であり、すでに優良企業として出来上がっている企業が、さらに業績を大きく伸ばして株価を何倍にも高める、というのはなかなか難しい話です。
確かに、過去のバックグランドデータでは、新しい株価指数はTOPIXに比べてアウトパフォームしているという分析結果が出てはいます(そもそもそうならなければ新しい指数を作るメリットがないためアウトパフォームするのが当たり前です)が、過去の結果が将来も同じように続く保証はありません。
現に、鳴り物入りで登場したJPX日経400の例をみても、同一の運用会社による過去2年間のTOPIX連動型ETF、日経平均株価連動型ETFとJPX日経400連動型ETFを比べると、日経平均株価型、TOPIX型のいずれの運用成績をも下回っているのが実態です。JPX日経400の銘柄選定基準では、ROEなど収益性の高い銘柄を組み入れているという触れ込みにもかかわらずです。
現時点での筆者の結論としては、少なくともインデックスファンドではなく個別銘柄に投資している個人投資家にとっては、新しいETFが設定されることへの影響は無視しても問題なく、何か特別な対策をする必要もないと判断しています。
もし、日経平均株価やTOPIXに比べて明らかに良いパフォーマンスを叩き出すことが判明したなら、その時に買えばよいと思います。
本資料は情報提供を目的としており、投資等の勧誘目的で作成したものではありません。お客様ご自身で投資の最終決定をおこなってください。本資料の内容は、弊社が信頼できると判断した情報源から入手・編集したものですが、その情報源の確実性まで保証するものではありません。なお、本資料の内容は、予告なしに変更することがあります。

足立武志
知って納得!株式投資で負けないための実践的基礎知識
株式投資がうまくいかない、という個人投資家の皆様へ。実践をベースにした「すぐに役立つ真の基礎知識」は、お客様の株式投資戦略に新たなヒントを提供。負けない、失敗しないためにはどのように行動すべきか、これから「株式投資」を始めようと考えている方、必見です。
国内株式のリスクと費用について
■国内株式 国内ETF/ETN 上場新株予約権証券(ライツ)
【株式等のお取引にかかるリスク】
株式等は株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。上場投資信託(ETF)は連動対象となっている指数や指標等の変動等、上場投資証券(ETN)は連動対象となっている指数や指標等の変動等や発行体となる金融機関の信用力悪化等、上場不動産投資信託証券(REIT)は運用不動産の価格や収益力の変動等、ライツは転換後の価格や評価額の変動等により、損失が生じるおそれがあります。※ライツは上場および行使期間に定めがあり、当該期間内に行使しない場合には、投資金額を全額失うことがあります。
レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意点
上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN(※)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
- レバレッジ型、インバース型のETF及びETNの価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
- 上記の理由から、レバレッジ型、インバース型のETF及びETNは、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
- レバレッジ型、インバース型のETF及びETNは、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただく、またはコールセンターにてお尋ねください。
※「上場有価証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し1日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
【信用取引にかかるリスク】
信用取引は取引の対象となっている株式等の株価(価格)の変動等により損失が生じるおそれがあります。信用取引は差し入れた委託保証金を上回る金額の取引をおこなうことができるため、大きな損失が発生する可能性があります。その損失額は差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
【株式等のお取引にかかる費用】
国内株式の委託手数料は「ゼロコース」「超割コース」「いちにち定額コース」の3コースから選択することができます。
〔ゼロコース(現物取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。
但し、原則として当社が指定するSOR(スマート・オーダー・ルーティング(※1))注文 のご利用が必須となります。(当社が指定する取引ツールや注文形態で発注する場合を除きます。)
ゼロコースをご利用される場合には、当社のSORやRクロス(※2)の内容を十分ご理解のうえでその利用に同意いただく必要があります。
※1 SORとは、複数市場から指定条件に従って最良の市場を選択し、注文を執行する形態の注文です。
※2 「Rクロス」は、楽天証券が提供する社内取引システム(ダークプール(※3))です。
※3 ダークプールとは、証券会社が投資家同士の売買注文を付け合わせ、対当する注文があれば金融商品取引所の立会外市場(ToSTNeT)に発注を行い約定させるシステムをいいます。
〔ゼロコース(信用取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。
但し、原則として当社が指定するSORのご利用が必須となります。(当社が指定する取引ツールや注文形態で発注する場合を除きます。)
〔超割コース(現物取引)〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引金額 取引手数料
5万円まで 55円(税込)
10万円まで 99円(税込)
20万円まで 115円(税込)
50万円まで 275円(税込)
100万円まで535円(税込)
150万円まで640円(税込)
3,000万円まで1,013円(税込)
3,000万円超 1,070円(税込)
〔超割コース(信用取引)〕
1回のお取引金額で手数料が決まります。
取引金額 取引手数料
10万円まで 99円(税込)
20万円まで 148円(税込)
50万円まで 198円(税込)
50万円超 385円(税込)
超割コース大口優遇の判定条件を達成すると、以下の優遇手数料が適用されます。大口優遇は一度条件を達成すると、3ヶ月間適用になります。詳しくは当社ウェブページをご参照ください。
〔超割コース 大口優遇(現物取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。
〔超割コース 大口優遇(信用取引)〕
約定金額にかかわらず取引手数料は0円です。
〔いちにち定額コース〕
1日の取引金額合計(現物取引と信用取引合計)で手数料が決まります。
1日の取引金額合計 取引手数料
100万円まで0円
200万円まで 2,200円(税込)
300万円まで 3,300円(税込)
以降、100万円増えるごとに1,100円(税込)追加。
※1日の取引金額合計は、前営業日の夜間取引と当日の日中取引を合算して計算いたします。
※一般信用取引における返済期日が当日の「いちにち信用取引」、および当社が別途指定する銘柄の手数料は0円です。これらのお取引は、いちにち定額コースの取引金額合計に含まれません。
【かぶミニ®(単元未満株の店頭取引)にかかるリスクおよび費用】
- リスクについて
- かぶミニ®の取扱い銘柄については市場環境等により、取扱いを停止する場合があります。
- 費用について
- 売買手数料は無料です。
かぶミニ®(単元未満株の店頭取引)は、当社が自己で直接の相手方となり市場外で売買を成立させます。そのため、取引価格は買付時には基準価格に一定のスプレッド(差額)を上乗せした価格、売却時には基準価格に一定のスプレッド(差額)を差し引いた価格となります(1円未満の端数がある場合、買付時は整数値に切り上げ、売却時は切り捨て)。なお、適用されるスプレッドは当社ウェブサイトにて開示していますが、相場環境の急変等により変動する場合があります。
- カスタマーサービスセンターのオペレーターの取次ぎによる電話注文は、上記いずれのコースかに関わらず、1回のお取引ごとにオペレーター取次ぎによる手数料(最大で4,950円(税込))を頂戴いたします。詳しくは取引説明書等をご確認ください。
- 信用取引には、上記の売買手数料の他にも各種費用がかかります。詳しくは取引説明書等をご確認ください。
- 信用取引をおこなうには、委託保証金の差し入れが必要です。最低委託保証金は30万円、委託保証金率は30%、委託保証金最低維持率(追証ライン)が20%です。委託保証金の保証金率が20%未満となった場合、不足額を所定の時限までに当社に差し入れていただき、委託保証金へ振替えていただくか、建玉を決済していただく必要があります。
レバレッジ型ETF等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、30%を上回る委託保証金が必要な場合がありますので、ご注意ください。
【貸株サービス・信用貸株にかかるリスクおよび費用】
(貸株サービスのみ)
- リスクについて
- 貸株サービスの利用に当社とお客様が締結する契約は「消費貸借契約」となります。株券等を貸付いただくにあたり、楽天証券よりお客様へ担保の提供はなされません(無担保取引)。
(信用貸株のみ) - 株券等の貸出設定について
- 信用貸株において、お客様が代用有価証券として当社に差入れている株券等(但し、当社が信用貸株の対象としていない銘柄は除く)のうち、一部の銘柄に限定して貸出すことができますが、各銘柄につき一部の数量のみに限定することはできませんので、ご注意ください。
(貸株サービス・信用貸株共通)
- 当社の信用リスク
- 当社がお客様に引渡すべき株券等の引渡しが、履行期日又は両者が合意した日に行われない場合があります。この場合、「株券等貸借取引に関する基本契約書」・「信用取引規定兼株券貸借取引取扱規定第2章」に基づき遅延損害金をお客様にお支払いいたしますが、履行期日又は両者が合意した日に返還を受けていた場合に株主として得られる権利(株主優待、議決権等)は、お客様は取得できません。
- 投資者保護基金の対象とはなりません
- 貸付いただいた株券等は、証券会社が自社の資産とお客様の資産を区別して管理する分別保管および投資者保護基金による保護の対象とはなりません。
- 手数料等諸費用について
- お客様は、株券等を貸付いただくにあたり、取引手数料等の費用をお支払いいただく必要はありません。
- 配当金等、株主の権利・義務について
- 貸借期間中、株券等は楽天証券名義又は第三者名義等になっており、この期間中において、お客様は株主としての権利義務をすべて喪失します。そのため一定期間株式を所有することで得られる株主提案権等について、貸借期間中はその株式を所有していないこととなりますので、ご注意ください。(但し、信用貸株では貸借期間中の全部又は一部においてお客様名義のままの場合もあり、この場合、お客様は株主としての権利義務の一部又は全部が保持されます。)株式分割等コーポレートアクションが発生した場合、自動的にお客様の口座に対象銘柄を返却することで、株主の権利を獲得します。権利獲得後の貸出設定は、お客様のお取引状況によってお手続きが異なりますのでご注意ください。貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金については、発行会社より配当の支払いがあった後所定の期日に、所得税相当額を差し引いた配当金相当額が楽天証券からお客様へ支払われます。
- 株主優待、配当金の情報について
- 株主優待の情報は、東洋経済新報社から提供されるデータを基にしており、原則として毎月1回の更新となります。更新日から次回更新日までの内容変更、売買単位の変更、分割による株数の変動には対応しておりません。また、貸株サービス・信用貸株内における配当金の情報は、TMI(Tokyo Market Information;東京証券取引所)より提供されるデータを基にしており、原則として毎営業日の更新となります。株主優待・配当金は各企業の判断で廃止・変更になる場合がありますので、必ず当該企業のホームページ等で内容をご確認ください。
- 大量保有報告(短期大量譲渡に伴う変更報告書)の提出について
- 楽天証券、または楽天証券と共同保有者(金融商品取引法第27条の23第5項)の関係にある楽天証券グループ会社等が、貸株対象銘柄について変更報告書(同法第27条の25第2項)を提出する場合において、当社がお客様からお借りした同銘柄の株券等を同変更報告書提出義務発生日の直近60日間に、お客様に返還させていただいているときは、お客様の氏名、取引株数、契約の種類(株券消費貸借契約である旨)等、同銘柄についての楽天証券の譲渡の相手方、および対価に関する事項を同変更報告書に記載させていただく場合がございますので、予めご了承ください。
- 税制について
- 株券貸借取引で支払われる貸借料及び貸借期間中に権利確定日が到来した場合の配当金相当額は、お客様が個人の場合、一般に雑所得又は事業所得として、総合課税の対象となります。なお、配当金相当額は、配当所得そのものではないため、配当控除は受けられません。また、お客様が法人の場合、一般に法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。税制は、お客様によりお取り扱いが異なる場合がありますので、詳しくは、税務署又は税理士等の専門家にご確認ください。